其の五 言の語らい
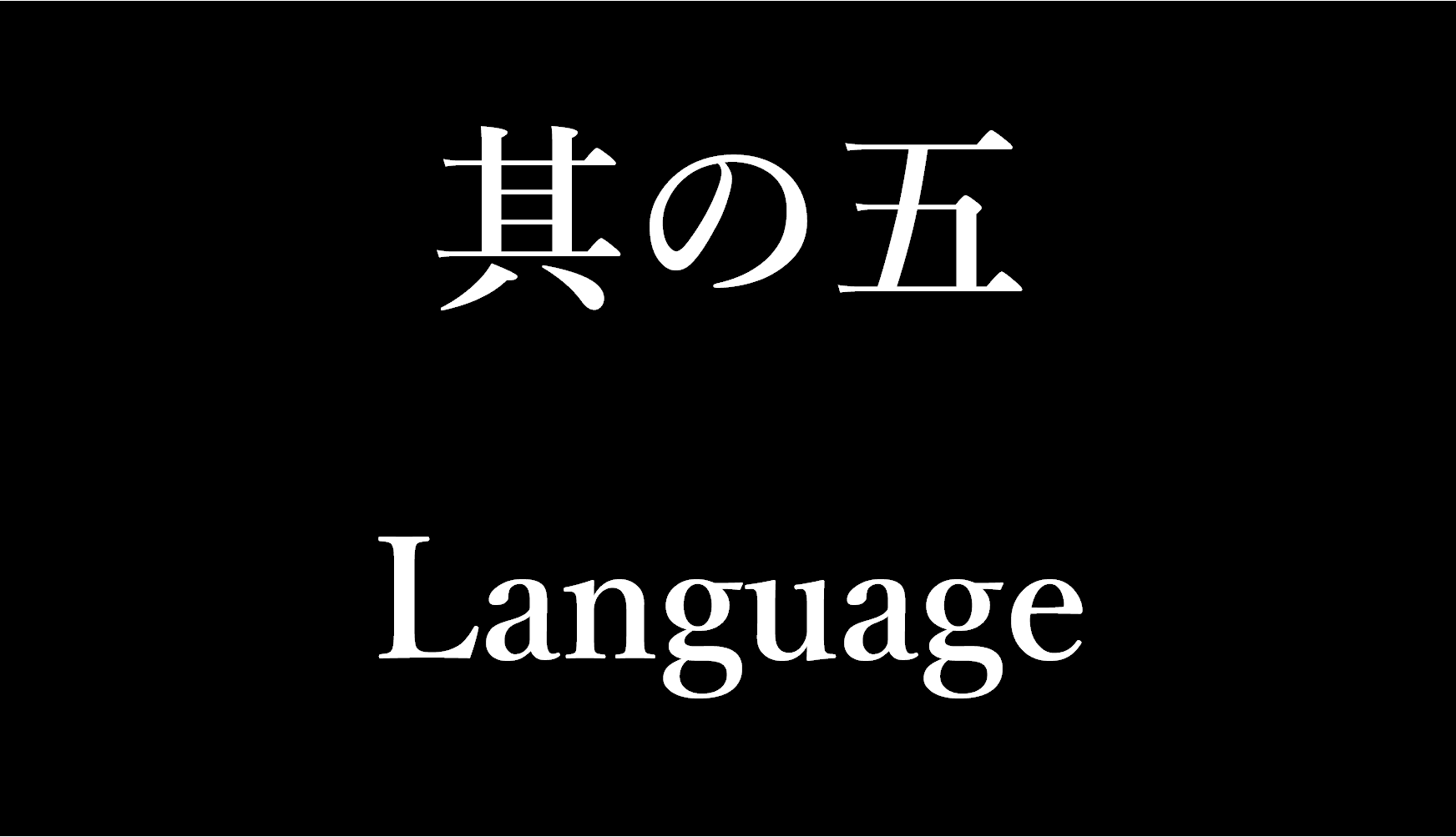
言の大樹に芽吹く語の葉
南アフリカ初の黒人大統領、ネルソン・マンデラは獅子吼した。
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.
相手が理解できる言語で話せば、それは相手の頭へ届く。 相手の母語で話せば、相手の心へ届く
言語を変えることで、相手の心に届く言葉がある。
同じ内容の発言でも、それが相手の母語か、その他かで響き方が違ってくる。
響き方が変わると、その効果も違ってくる。
この効果の変化は、身近な人間関係のみならず、政治や経済、教育の世界でも同じだ。
何故なら、詮ずる所、それらは人の判断、即ち、感情、欲望、野望、希望といったものに左右されるからである。そしてそれらは全て人の心と密接している。
つまり、最後に人を動かすのは理屈ではなく心なのだ。
言語の幅を広げることは、それ程の力を得るということ。
世界の漢塾 Global Otokojuku の塾生たるもの、言語の幅を広げ、言葉の力をつけよ。
言葉を洗練せよ。
おんどれすんどれ言うてる場合とちゃいまんがな。
鋼の塾則を暗唱しなおせいっ!
母語がマイナー言語である強み
アフリカには五十幾つの国があり、その母語は二千を超える。
人類、民族の歴史を刻んできた言語の大樹を、今もなお、大切に育んでいる。
一方、世界的に見ても、共通言語を重視するあまり、母語が消えてきたことも事実。
そして今も消えつつあると報告されている。 我が国日本でも北海道のアイヌ語が消滅の危機にある。
時代の変遷と共に枯れ落ちた葉を、大樹の養分と成すかは、我々人類に託されている。
マイナー言語を知っているということは、大きな強みである。貴重な人材だ。
6つの国連公用語を習得することも確かに強みではあるが、彼らが束になっても北海道アイヌ語で会話できる希望は薄いだろう。
逆にそれらの公用語は、どこへ行こうとも、誰かしら、どれかを理解できてしまう。言語そのものの利便性はあっても、それを話せること自体に、それほどの強みはない。
国連公用語を極めるのであれば、他に何かもう一つの専門知識を持たねばならない。国をまたいでも通用する分野、例えば、医療、金融、IT、エネルギーに関する専門知識を極めよ。
万里の道も一歩から
母語とは、幼少期より自然と習得する言語。
言葉の機微が、話者の機微が、自然と伝わってくる。翻訳処理をする必要もない。故に母語は心にすっと届く。
言語の幅を広げるとこは、自分の世界を広げることに直結する。
英語なんか苦手やし。
と、思うのであれば、日本語に近い韓国語でもいい。中国語でもいい。消滅しかけている北海道アイヌ語でもいい。
世界中の「こんにちは」と「ありがとう」だけを習得しても良い。
「そんなん使わんかったら意味ないやん?」
その通り。使え。
日本人同士でも「サンキュー」と言うように、相手の国籍を問わず、使ってみると良い。
それで少しずつ世界は開ける。
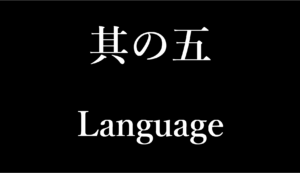
シェアする前に考えろ
漢になっちまうぜ?